最近、「幼年期の終わり(幼年期の終り)」という小説を読んだので、その感想を書いてみました。
以下、今回の内容です。
- 幼年期の終わり(幼年期の終り)とは?
- 第一部から第三部まで、それぞれのあらすじとネタバレを含めた感想
- 各部、どこが面白くてどこが微妙だと感じたか
ところで、Googleで「幼年期の終わり」と検索すると、その後に「つまらない」と出てきませんか?
そこで、各部ごとの感想に、面白かった部分と微妙だった部分も素直に書いてみました。
幼年期の終わりが気になっている方は、ぜひ最後まで見ていってくださいね。
それでは、本題に入りましょう!
幼年期の終わり(幼年期の終り)とは?
幼年期の終わりは、イギリスのSF作家「アーサー・C・クラーク」氏の長編小説になります。
アメリカでは1952年に、日本では1964年に福島正実さんの訳で「幼年期の終り」として早川書房から出版されました。
その後も、複数の方に訳されて出版されています。
地球に到来した高度な知能の異星人によって、100年以上管理されていく話
時は米ソ宇宙開発競争時代、各国の主要都市上空に突如として巨大な宇宙船が出現したところから物語は始まります。
普通はそこから戦いが始まりそうですが、この作品に限っては戦いは起こらないんですよね。
高度な科学技術を持つ異星人に地球側からの攻撃はまったく通用しませんし、異星人側からは侵略はおろか、先に地球側が攻撃してきたことへの報復すらないのです。
むしろ、地球人に新技術を与えたりと、異星人は友好的に接してきます。
- 異星人が地球に来る前の状況を短く書いたプロローグ
- 姿は見せないものの、異星人がコンタクトを取りながら技術を提供してくる第一部
- 地球はユートピアのようになっていて、ようやく姿を見せた異星人と共存する第二部
- 異星人の目的が明かされ、地球の最後とともに結末へと向かう第三部
という構成からなっている物語です。
実際に読んでみて、つまらなかったのか?
はっきりいって、面白かった!です!
- 異星人が地球に来た目的や、行動原理
- 地球や地球人はどこへ向かっていくのか
といった謎が、最初から最後までずっと気になりながら読み進められましたね。
それに、半世紀以上前の作品とは思えないほどワクワク感が楽しめました。
当たり前のように言ってますけど、これってめちゃくちゃすごくないですか?特にSF作品だと、古臭さが出てつまらなくなりそうなのに、そういった欠点がまったく感じられなかったんですよね。
あえて悪い部分をあげるとすれば、
- 登場人物が多いうえに、海外作品のため名前が覚えにくい
- 第三者視点(神視点?)なのに彼などの代名詞も多用されていて、誰のセリフかわかりづらい
- 出てきたばかりの人物だろうと会話が長く、退屈なこともあった
こんな感じですかね。
全体の概要はこのへんにして、次は各部ごとに見ていきましょう。
第一部のあらすじと、ネタバレを含めた感想
冒頭でも触れたとおり、異星人側は高度な科学技術を持っていながらも、地球を侵略したりはしてきません。
それどころか、新たな知識や技術を与えてきたことで、地球はどんどん豊かになっていきました。
やがて、地域区分的な名称は残っているものの、世界全体は統一されて異星人に管理されているような状態になります。
カレルレンと名乗った異星人の代表は、電波を通して、流暢な英語を使って地球人に親しく挨拶なんかもしてきました。
しかし、
- 姿を見せない異星人の、秘密主義的な態度への不満
- ほとんど無条件に、異星人が地球を発展させていく真の理由
- 小さな文化や伝統が消えてしまうことへの危惧
などを考える地球人も少なからずいて、異星人に対する不満が書かれているのでした。
ただし、50年後に地球人の前に姿を見せることを約束してきます。
没入しながら物語を追うことができて面白かった
どういうことかと言うと、半世紀以上前とはいえ、地球の状態は今とあまり変わらないと思うんですよね。
そのため、もし攻撃的でない異星人が現れたら・・・といった想像をしながら物語を楽しめました。
地球人の中には過激派?な人たちも出てきたりして、実際にありそうだなと思いながら読み進められましたね。
それから、現代科学を超えた異星人の技術が書かれている点もSFの魅力というか、本作の魅力でもありました。
ただし、魔法ではなくあくまでも科学技術だということは強調されていましたね。
そういった点を考慮しながら、異星人をどうにか欺こうとしている人もいるところとか、ドキドキしながら読めました。
人物が多くて名前が覚えにくいのと、会話が長く感じられた
海外の小説だから仕方ないのはわかりますけど、やっぱり人名が覚えにくかったですね。
それに、結構いろんな人が出てくるんですよ。
そのため、名前を覚えるのは後にして、会話だけ追うようにして読み進めました。
中にはあまり重要ではない人もいるでしょうしね。
あと、海外の映画?を彷彿させるような会話のシーンとかあって、あまり興味がわかない内容でも話が長かった印象です。
とりあえず、異星人の動向だったり、異星人を嫌う人たちの行動を中心に読んでいきました。
第二部のあらすじと、ネタバレを含めた感想
第一部から50年後、世界各国の主要都市上空に浮かんでいたはずの宇宙船は突然姿を消し、ニューヨーク上空のものだけとなっていました。
地球人には何が起きたのかわかりませんでしたが、約束は守って報道記者の前に異星人は姿を現します。
巨体に翼と角と尻尾という、悪魔のような見た目をしているのでした。
しかし、50年という年月のうちに人類は異星人を受け入れていて、中には異星人と交流関係をもった人も出てきます。
ただ、ここでも不満をもつ人はいて、その主な理由は宇宙開発が禁止されていたからでした。
そんな人物のひとりであるジャンは、とあるパーティで降霊術のようなものに興じながら、異星人の母星について質問します。
出てきた答えは、距離にして40光年(光の速さで40年)も離れている星なのでした。
しかし、異星人の宇宙船はきわめて光速に近い速さが出せるため、相対性理論によって搭乗者の感覚では数か月程度で移動できるのです。
ジャンはクジラの標本の中に隠れて、異星人の星へと密航するのでした。
何かに引き寄せられていくような感覚と、異星人の母星に向かうところが面白かった
降霊術という、唐突なオカルト要素が出てくるんですけど、もちろんその場に居合わせた人たちは信じていたわけじゃないんですよ。
しかし、異星人の母星を質問した時に答えが得られたことで、おふざけのような雰囲気だったのが一変します。
このあたりからの未知なる存在に引き寄せられていくような感じが、読んでいて面白かったですね。
それから、異星人の母星へと密航するシーンも、うまくいくのかどうかというドキドキ感が味わえました。
第二部は第一部から50年後のため、当然新しい人物ばかりになるんですよ。
それでも、
- 異星人とも違うような、未知なる存在の示唆
- 異星人の母星へと密航するという急展開
といった部分でかなり楽しめました。
登場人物が新しくなるため読んでいて大変、ストーリーにはご都合主義感があった
何度も申し上げているとおり、第一部と第二部では登場人物が大きく異なります。
- 再び名前を覚えなければならない
- 出てきたばかりの人物なのに、長いやりとりを見なければならなかった
といった点で大変でした。
それから、第二部はいろいろとご都合主義感がありましたね。
唐突に出てきた降霊術が異星人の母星を答えてくれたり、異星人にバレずに密航できたこととかです。
第一部では、異星人を欺けると自信をもっていた地球人の計画は、次々と見破られていましたからね。
そういった意味でも、第二部はいろいろ都合がよすぎると感じていました。
しかし、第三部でなされた説明を読んで、モヤモヤが半分くらいは解決しましたね。
というわけで、第三部の説明へと移りましょう。
第三部のあらすじと、ネタバレを含めた感想
違和感のある出来事に遭遇したことで、異星人に監視されているんじゃないかと感じた家族が登場します。
程なくして、家族のうちの幼い子供に、
- 夢を通してはるか彼方の宇宙を見ることができる
- 超能力のように周囲の物体を操ることができる
といった異質な能力が発現していくのでした。
そんな悩みを抱えた家族に、異星人側から会見が申し込まれます。
そこでは、
- 異質な能力が芽生えたりした変化は、世界規模で幼い子供たちに発生すること
- 異星人の目的は、そういった子供たちの変化(進化)を見守ること
- 異星人自身はもう進化できないこと
- 異星人は、更なる上位存在に命じられているだけだということ
などが説明されました。
その後、進化が起きた子供たちが世界中で現れると、異星人の手によって隔離・保護されるのでした。
場面は変わり、異星人の星に到着したジャンが見た光景と、帰還するまでが書かれていきます。
約80年が経過した地球(ジャンの感覚では数か月)には、進化した子供たち以外に誰も残っておらず、異星人の口から地球で起きた出来事が語られるのでした。
そして、進化した子供たちの力はついに月の動きにまで影響を与えます。
太陽にも影響を与えるかもしれないと危惧した異星人は、地球からの脱出をしました。
ジャンは自らの意志で地球に残ると、異星人に託された最後の役割として、見聞きしたすべてを電波で異星人に送ります。
子供たちが旅立とうとするのと、地球が壊れていくさまを、ジャンは目の前で見届けるのでした。
異星人の理解すら及ばない変化と、奇妙な星々について書かれているのが面白かった
地球人よりはるかに高度な知能をもつ異星人ですが、そんな異星人ですら困惑するような勢いで子供たちの進化が書かれていきます。
それから、地球とはかけ離れた環境の星についての描写も面白かったですね。
ジャンが異星人の星を見て回るシーンとか、進化した子供たちに芽生えた能力ではるか彼方の星を具体的に見ていたシーンとかです。
異星人の境遇については、かなり悲しい気持ちになりました。
というのも、異星人自身は進化できないのです。
- 小さな文化や伝統が失われる
- 進化した子供たちは、もはやそれまでの子供たちではなくなる
といったことに悩み、絶望する地球人の気持ちも痛いほどわかりました。
しかし、進化を見守るのは地球人が5回目だという異星人の、地球人がうらやましいという言葉は重みが違うように感じましたね。
それから、第二部でモヤモヤしていた点を説明してくれたのもよかったです。
たとえば、降霊術でいろいろわかったのは、後で進化する子供たちが生まれてくる前にもかかわらず、時を超えて伝えていたという感じでした。
いろいろ矛盾していそうですが、時間という概念は複雑だということも一緒に語られていましたね。
第二部の項目でモヤモヤが半分くらいしか解決していないと書いたのは、説明されてはいるものの完全な納得まではいかなかったからです。(私の理解力が低いだけかもしれませんが・・・)
もうひとつ、ジャンが異星人にバレずに密航できた理由ですが、わざと見逃していたんじゃないかとほのめかす描写がありました。
こちらは、スッと飲み込めましたね。
急展開が起きるまでが長いのと、話が難しいのが読むうえで大変だった
第三部は、子供たちに変化が起き始めてからは一瞬で読み進めてしまいましたが、そこまでいくのに結構退屈でした。
というのも、第二部の最後はジャンが宇宙に飛び立つシーンでワクワクしていたのに、第三部の始まりでは日常の光景を書いた場面に切り替わるからです。
そして、これがまた結構長いんですよ。
見返してみれば第三部の後半に関係していることはなんとなくわかるのですが、初見では正直退屈でした。
ジャンがどうなるのか気になっていたのもあって、お預けはかなり焦らされましたね。
ただ、物語の結末を知った後では、上で説明したような構成にも納得しました。
- 子供たちに起きていく変化
- ジャンが宇宙を旅して帰還するまでのシーン
- 地球、そして物語の終わり
といった、畳みかけるような第三部の後半の面白さも、構成あってのものだと思いましたね。
ただし、第三部は特にわかりづらいというか、やや話が難しかったです。
途中途中、雰囲気だけ楽しみながら読み進めたりもしました。
およそ半分くらいの理解と、まったくわからないわけでもなかったので、なんだかんだ雰囲気だけでも楽しめたのだと思います。
まとめ
今回の内容を簡単に振り返っていきましょう。
幼年期の終わり(幼年期の終り)は、
- 異星人が地球に来る前の状況を短く書いたプロローグ
- 姿は見せないものの、異星人がコンタクトを取りながら技術を提供してくる第一部
- 地球はユートピアのようになっていて、ようやく姿を見せた異星人と共存する第二部
- 異星人の目的が明かされ、地球の結末へと向かう第三部
と、プロローグ足す三部で構成されたSF小説です。
なお、記事内では固有名詞を使わないように「異星人」などと書きましたが、
- 異星人は、オーバーロードまたは上帝
- 異星人たちに命令を下していた上位存在は、オーバーマインドまたは上霊
と、小説では表記されています。
かえって理解を妨げていましたらすみません・・・。
以下、総評です。
読みづらかったり退屈だったシーンもありましたが、面白いところはものすごく面白く、引き込まれました。
半世紀以上前に書かれたものとは思えないほど楽しめた作品で、読後感も十分です。
最後まで読んでみて、つまらないなんて感じたことはありませんでした。
- 設定が気に入った方
- 大まかな流れを見て、もっと知りたくなった方
- 自分の目で全編読みたい方
ぜひ、お手に取ってみてはいかがでしょうか。
複数の方に日本語訳されていますので、いろいろチェックしてみてくださいね。
同作者の小説「2001年宇宙の旅」についての感想記事もありますので、よかったら見ていってくださいね。
最後に
ここまで見ていただきありがとうございます。
久しぶりに小説を読んだので、せっかくならとブログのネタにしてみましたが、いかがだったでしょうか。
どれくらい久しぶりかというと、小学生時代に読んだタイムマシンというSF小説くらいしか記憶に残っていませんw
普段は二次元ばかりの俗な私が、なぜこんな高尚な?小説を読んだのかと言いますと、「ひねくれひで」という淫夢系MADで名前が出ていたからですね。
ひねくれひで大会編④.ep11 – ニコニコ動画 (nicovideo.jp)
上にある11話の5分30秒くらいからGOが引用しています。
サイコパスというアニメでも哲学書とか引用されていましたけど、そういった何気なく見ていたものにステマ?されると弱いんですよね・・・。他には、好きなYouTuberなんかが飯テロとして上げた動画に出てくる商品とか、めちゃくちゃ食べたくなります。広告として宣伝するよりも、はるかに威力が高いと思うんですけど、わかってくれる人いませんかね?
少し話がそれてしまいましたが、多分この先も本の紹介をしていく予定です。
ブログのネタが尽きないよう、精いっぱい頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。
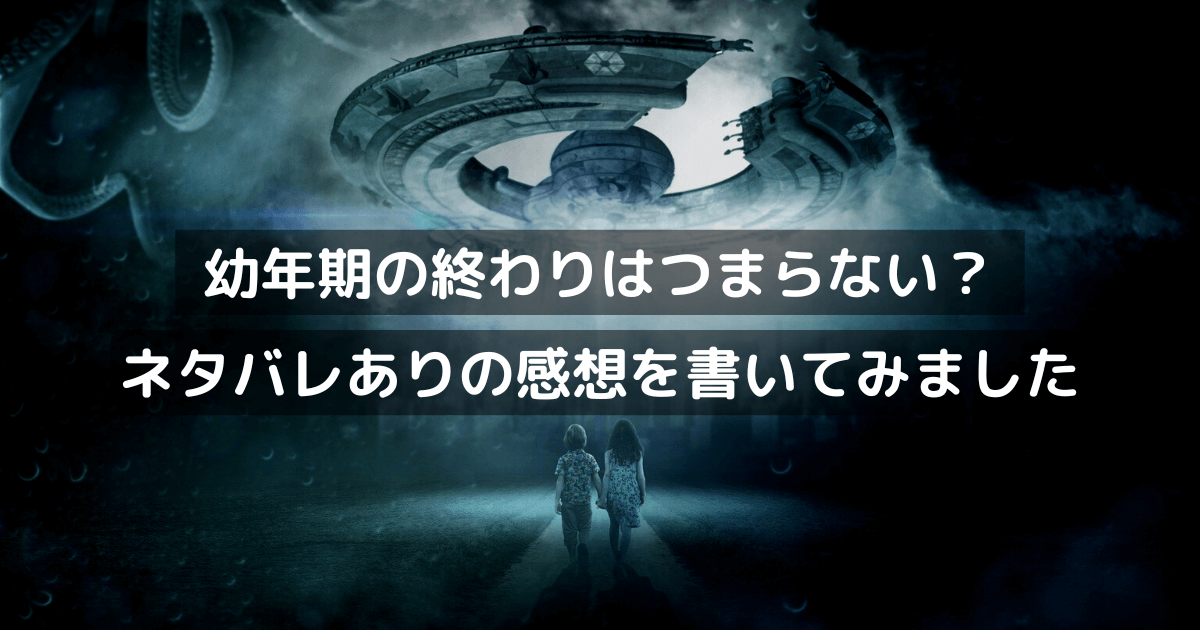
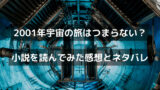
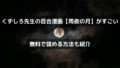

コメント